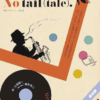<観劇レポート>藤一色「七転十倒」
【ネタバレ分離】昨日観た芝居、 藤一色「七転十倒」の観劇レポートです。

もくじ
公演前情報
公演・観劇データ
| 項目 | データ |
|---|---|
| 団体名 | 藤一色 |
| 回 | 藤一色 第十一色公演 |
| 題 | 七転十倒 |
| 脚本 | 遠藤遥風(藤一色) |
| 演出 | 加藤広祐(藤一色) |
| 日時場所 | 2022/10/19(水)~2022/10/23(日) シアター711(東京都) |
団体の紹介
劇団ホームページにはこんな紹介があります。
藤一色(ふじいっしょく)は、
2015年に主宰・遠藤遥風と加藤広祐を
中心に旗揚げした劇団です。「遠くないファンタジー」を
コンセプトとして掲げ、
虚構と現実の境を曖昧にし、
見る人を肯定する物語を創り出しています。
過去の観劇
- 2024年03月22日【観劇メモ】藤一色 「三角形の世界の中の」
- 2023年04月08日藤一色 「紙は人に染まらない」
事前に分かるストーリーは?
こんな記載を見つけました
どう考えてもおかしい
今か昔か、とあるところに限界集落がありました。
村民の興五郎は言いました。
「井の中の蛙、井の中にして大海を制す。オラは村おこしに乗じて天下を取る」
一進一退七難八苦、寝ても覚めても七転十倒。
無から有を生み出そうとした、とある創作者達の物語。
ネタバレしない程度の情報
観劇日時・上演時間・価格
| 項目 | データ |
|---|---|
| 観劇日時 | 2022年10月21日 19時00分〜 |
| 上演時間 | 90分(途中休憩なし) |
| 価格 | 3500円 全席自由 |
チケット購入方法
劇団のホームページからのリンク先で予約しました。
当日受付で、現金でお金を支払いました。
客層・客席の様子
男女比は7:3くらいでシニア男性が多めでした。
観劇初心者の方へ
観劇初心者でも、安心して観る事が出来る芝居です。
・会話劇
・考えさせる
観た直後のtweet
藤一色「七転十倒」90分休無
めっちゃ面白かった!けど好き嫌いバックリ割れると思う。小劇場や創作好きに刺さりそう。ある事を語ってるのに、ある事が結局出てこない。外堀を埋めることでそれが際立つ。不条理的、屁理屈的、ブラックコメディ的。そして迷いと愛に溢れてる。役者粒揃い。超オススメ! pic.twitter.com/zz7nNrH8cn— てっくぱぱ@観劇垢 (@from_techpapa) October 21, 2022
満足度
(5/5点満点)
CoRich「観てきた」に投稿している個人的な満足度。公演登録がない場合も、同じ尺度で満足度を表現しています。
感想(ネタバレあり)
ダムに沈んでしまう候補になりそうな、ド田舎の村。村おこしに、「何か面白いもの」を作るぞと回覧版を回したら、集まってきた面々。どうやら、「演劇」のようなものをみんなで創作しているらしいが、何を作っているのかは一向に分からない。でも、ある一つの物語をみんなが作ろうとしている、らしい。ただ、村おこしイベントの申請日を間違えたり、伝染病が流行ったりして、その作品はお披露目されず。実は集まった面々は、村にいる妖怪が、人間のふりをして集まってた、らしい。ダムに沈む村の中から、これじゃ終われねえ、とYoutubeを配信してみるも・・・な作品。
劇団初見。とても面白かった。ストーリーをあらためて強引に書き下してみると、何だかよく分からないけれど、観ていて不明確な部分はあまりなくて。むしろ、冷静に考えるとよく分からない事を、気がつくと信じてしまっている自分がいる感覚。冒頭あたりの会話から、どうもこの面々は人間じゃないんじゃないかなぁ、なんて事は薄々気がつくのだけれど、違和感を投げかけつつも徐々に種明かししていく物語。
村おこしに作っている「物語」・・・について、それが「演劇」だとか「小説」だとか、あるいは「映像作品だ」という、何を作っているのかが一向にに語られない。それなのに、「よい物語」の書き方とか、「物語」と「作品」は何が違うのかとか、「すべての物語の原型は、シェークスピア時代に完成している、何ていうのは傲慢な誤解だ(うろ覚え)」なんて事を、登場人物たちは「たのしいもの」を作りながら、延々と語っている。「演劇」という言葉のフチを歩くように、出すことを避けたまま、それでもそこで語られているのは、明らかに「演劇」であり、あるいは「映画」のような物語創作。
そんなフチどり方をみていると、不条理な演劇のようにも見えてくるし、あるいは、演劇に対して「屁理屈」をこねているようにも見える。あるいは、最後に出てくるコロナとおぼしき伝染病からも、この作品自体が全てブラックコメディのようにも見えてくる。不思議な会話のやり取り。その背後に、演劇であったり物語創作に対する、コロナ禍で被った諸々のネガティブな事象と、それを上回るような愛情とが、透けて見えてくる。よく見かける「演劇への愛を語る演劇」は、よい作品でも、常に若干の気恥ずかしさが付きまとうけれど、あの恥ずかしい感覚もフチを通って避けながら、いい塩梅に描いた作品だった。